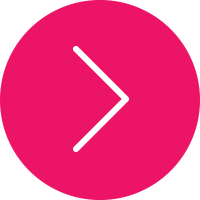主な作品について about Works
— 想像力が体の感覚と
発酵してくるものに逢える
抱き合わされると
また不意に滑り込んでくる
メッセージも受ける
人の力を超えたものに助けられる
時の中で作品のかたちになる—
「土偶 - JOMON 」1967年
ひょうひょうと風の吹き荒ぶ音。
「キィーン...」と、生ま木が立ったまま裂ける音が沈黙をきわだたせ、太古の雄たけびがあたりにこだまする。日本の古代遺跡から発掘された、土で作られたやきものの人型である土偶。原始時代、縄文のプリミティーブな大地の生命力を表そうと作品に思いをこめた。
死者のお供として土偶を使用する以前には、生きながら地下に埋められた人々がいたと言い伝えられ、その人々の泣き叫ぶ声が地表に聴こえたともいわれる。そんな話にも、わたしのイメージは撓められた。
疑いもなくエネルギーを外側にばらまく西洋のダンサーたちに対抗したわたしが、下へ下へと降りて行き膝でいざり、伏す、這う、倒れる、そして物体として立つことになった作品である。
1969年の五月、マンハッタンのカウフマンホールで初演したこの作品は、秋には東京の虎ノ門ホールでも上演し、その年の文部省芸術祭奨励賞、舞踊ペンクラブ賞、音楽新聞新人賞を受けた。
己の声か 誰の声か
人々のざわめきがおさまり、楽器のチユーニングが止み、指揮者が手を振り上げる寸前、
あの異様なサイレンツ。わたしは思わず叫びそうになる怖さにおののく。
突然にやってくる得体の知れないものはとても怖い。
また、どこからともなくふと聞こえてくる声も....
しかし、時のまにまにメッセージのように湧いてくるアイディアは、心当たりがして体に響くこともある。それらの彼岸はとらえにくいが感動的で得難いおいしいものでもあり、私はそれを受けた。
若い頃からこんなことは起っていたが、1967年の夏、悩み続けていたニューヨーク公演
"土偶 (JOMON) "の振付け中、矢継ぎばやに動きが決まり、作品ができてしまった。
結婚、妊娠、子育てがつづき、1975年の初夏、次は作品 "鳥 "。
踊る自分の姿が現れた。3回曲をかけ直したが、3回とも全く同じ動きが視える形で現れた。
無意識の底にあったものの浮かび上がりか? 天空からの指示なのか?
よく判らないまま時が過ぎた。
子供たちが10歳になった頃には、"舞踊論"シリーズが終わり、衣裳と仮面作りの楽しかった"VOICE"シリーズが続く。
「鳥」1975年
1975年の9月に、作品「鳥」はニューヨークのバーナード・カレッジで初演した。
一度上演すると、つづけていくつもの舞台で踊るよう所望された。百人の小ホールから二千人入るセントラルパーク・デラコルテ野外劇場まで、様々に異なる条件での「鳥」。
一回ごとに、新しい作品としてうまれかわる。瞬間瞬間に、飛び散り砕ける波動のようなものと体がせめぎ合い、舞台空間の不可思議な、まさに異次元的なその場を、もう一度、もう一度...と、何回も希い、1994年の秋まで踊った。
九十六歳で世を去ったパブロ・カルザスが、アンコールには必ず弾いたといわれる、彼の生まれ故郷、カタロニアの民謡の旋律である。清々と透明で、わずかにほろ苦さを含むシンプルなこの短い曲を、くり返しくり返し聴きながら、わたしは内部から惹きおこされるわたしの動きにめぐり会った。翔べても翔べなくても翔ぼうとする意志...。
反復の中で主題は螺旋状に上昇している。必然的な動きが溢れでた。
"鳥"は1975年より1997年まで20年間を踊りつづけてダンサーとして舞台を降りた。
蘇る体の記憶
現代作家の作品に触発されながらも、ヨーロッパ文明のあり余る贅沢なものにも染まっていて、特に曲の華麗な美しさに引き寄せられ、遂にクラシックや民族色の濃いものに傾いた。
西洋の旋律とリズムであっても、呼吸(息)の “間”によって動くと体になじみ、和む。
ゴシック建築の美しいカテドラルがニューヨークにはいくつもあるが、すでに礼拝には使用されていない大理石のカテドラル、グレートホールで踊る機会が度々訪れていた。現代舞踊家でありながら、さっさと現代音楽から踵を返し、プリ・クラシックや民族音楽に傾いた私は、その場に身をおくだけでいくつかの作品のアイディアに恵まれた。
これは己れの意識の固さを少しでも解くために、日々インプロバイゼーション=即興表現を試み、くり返し心がけた25年余りの年月の賜物だったと思う。
クラシックの厳密な体型の中でも自由(フリーダム)が私の中の必然性を掴みだしてくれた。クラシック音楽をそのまま使用したのは、当時流行の機械音楽を好きになれなかった反動だろうか。
「一人のためのデュエット」 1983年
心のおもむくままに毎日インプロバイゼーションで踊った。次第に自然に動きが曲と馴染むのを待った。「好きな曲は踊っておきたい!」と50歳の数字に慌てた私は、ブラームスを毎日聴いた。
少女期に聴いて忘れられなかったチロル地方の民謡のような “ワルツ”、あのブラームスの “ワルツ”。
時は足早に行ってしまう…..今、踊らなければ。50歳を迎えた今こそやっと踊れる!と思いこみ、「一人のためのデュエット」と題して、“ワルツ” “バラード” “間奏曲”を踊った。動けるうちに好きな曲は…と思い、次々と作品 “アリア” “カノン” “ララバイ”とつづく。
「ララバイ」1987年
この作品は、セーヌ川に身を投じたユダヤ人の詩人、パウル・ツェランの残した作品の断片からのイメージがもとになっており、”さまよう魂への子守り唄(ララバイ)”の踊りだった。
イスラエルの古い子守り唄をうたう女性のヴォーカルと、終わりに急に曲をドボルザークのマーチに変えたのは、戦地に散った息子の帰りを待つ母親が、マーチを聞くと狂うように街をさまよったという話が、どうしても私の身体から離れなかったからだ。
自分の知覚と記憶が呼び戻され、発酵して不意に自分の中に滑り込んだ作品であった。
「Voice」1985年
黒衣の装束のドラマ
1986年の夏、東京、大阪、名古屋で、作品「VOICE VII」は遂に60個の仮面たちで踊った。いや100個全部。仮面を顔の前後や腰につけたり、手で持ったりして、一人で二つも三つも使う人がいた。他人の目を気にしすぎ、意識の硬い日本人たちが、仮面で顔を蔽い隠したことで、なんと自由に己れを解放したことか。それまでの人格とは全く違う踊りをした者すらいた。お酒の力を借りなくては羽目をはずせない祭り好きの日本人の本性を、わたしは見た思いだった。
ただ黙々と歩みを進める人々の長い列。どこから来て何処に行くのか、誰もわからない。しかし、運命られている軌道を、人々が蜿蜒とつながって行く…山あり谷あり、道なき道をも人は旅行く。
そんな姿を、わたしは作品にしたかった。動きは一人一人のもの、それぞれの創意により自由に振る舞ってよいことにしたが、一歩一歩がフィルムの一こま一こまを見るように、ストップ・モーションをとりいれた動きをリズミックに踊ることが条件であつた。 曲のリズムを活かすムーヴメントなら、拍数を引き伸ばしても、刻んでも、ゆっくりと進んでも、前の人を追い抜いてもよし。しかし、宇宙の法則ででもあるかのように、原則として、必ず決められた軌道を進む。
世の習わしや方向に従ったり、あるいは背いたり、笑い転げ、惑い、転び、時には寝てしまったり、怠けたり、喧嘩もして逸脱したりもするが、その歩みは、歩み固められた先人の道を行く。まるで、日本の古典的巡礼である〝熊野詣で〟の蟻の門渡りのように列になって続く。誰かが止まると全員が立ち止まり、一切の身動きをしないという時間の止まる瞬間も挿入。そして、また誰かが歩きだすと皆がそれに続く。
亡者どものように影絵のかたちでわたしの脳裡に、刻まれていた、日本の遠い昔の盆踊りが、眼前にくりひろげられた。作品の始めは犬も子どもたちも全員を黒衣姿の黒装束にした。黒い前垂れのついた頭布で頭と顔を覆い、手っ甲と脚半をつけた手首から先と足首から先だけがみえる以外は、全身黒ずくめである。
全身黒ずくめの歌舞伎の黒衣は、視えないもの、という約束ごとの上になりたっている日本独特の装束で、この型が、歌舞伎の舞台上では、舞台役者を助ける裏方であるが、その黒衣をわたしは、ダンスの主役に置き換えた。人間の中の目に見えないスピリットを引き出すこと、動きの抽象性を際立たせること、そのためには、顔無し、姿無しのこの黒衣の装束ほど物を言う衣裳はない。
実際、生まの体や顔を覆うことによって、内面の表情がいっそう鮮やかに形になった。一見して、一律なアブストラクトの効果を持ちながらも、一人一人の顔が違うように、それぞれの個性が逆に際立って動きから飛び出してくる。むき出している手と足は、照明によって更に人々の動きを強調した。
回転速度を操作した十三世紀のスペインの宗教音楽を使ったが、それは天使の声にも、また、魔の声にも聞こえるもので、六人の男女の混声は弦の響きとともにこだました。中間部にさしかかろうという時、突如、その音をわたしは カット・オフする。動きを止められた人々は、サイレントのなかで身動きせず、沈黙をまもる。やがて、シュールな響きの歌声とともにスローモーションのヴィジョンよろしく、地に吸い込まれるように、ただ、下に下にその形のまま膝をゆっくりと折り曲げて沈み込んで行き、舞台の床に全員が伏し倒れる。変容のときのなか…人々は重なりあったり、うごめいたりしながら、地を這った。混沌とした混声のアンサンブルの中で、それぞれが這いながら黒装束を脱ぎ捨てていった。黒い色が徐々に剥がされていく。
作品後半の展開のために、この作品では黒装束の下に、肌色の仮面と、ベージュ系の濃淡でさまざまにデザインした衣裳を重ね着にしていた。一人として同じ衣裳ではないベージュの衣裳を着た人々をくまなく照らしはじめた舞台照明。黒衣の衣裳の下から鮮やかに現れ出た、黄金色の生命の輝き。新しいいのちを得た人々は再び列になって歩み、舞いはじめた。
いたずら悪魔や、神になるシーンがめぐり、舞い上がるベージュ色の仮面たちの群れ。曲は延々とひびき続く。すべてが黄金色に光り輝く舞台は、次第に赤々と燃えあがる炎のように照明効果で染められ、揺らめくなかで、なおも仮面の人々の列がとぎれずに舞い狂うシーンを、ゆっくり、ゆっくりと、闇のなかに溶けこませて作品は終わる。
「翔 」 1988年
神を招く笛の音が空を切り裂く。確かに能管の音に魅せられたことを、しかと体が自覚した。
1987年夏のはじめに、能楽笛方宗家のひとつ藤田流第十一代家元に、わたしは面会を申し込まれた。
お目にかかるなり、家元が鳴りひびかせた能管の凄まじい音に、わたしは圧倒された。能管の響きは神を招くためであり、人の体には危険に感じられる。その時、熱田神宮能楽殿での公演企画に、わたしは招聘された。
五十四歳の秋に、わたしははじめて能舞台に立った。<三条万里子幽玄空間に舞う>と題され、“能舞台との交響”という副題をつけられたいかめしい企画の第一回目であり、非常に怖い舞台であった。“芸の原点は神への祈りであった。神の地に繰り広げる、舞台芸術のシリーズ”と公演のパンフレットに書いた企画者の言葉は重い。
橋がかりの重要さと舞台との関係、舞台の形とサイズ、それらの必然性にわたしは驚く。使い込まれた舞台から先達の力をいただいた。
様式性と象徴美を大切にしている伝統ある能舞台。頭から顔につけたのは、平織りの白い組み紐を考案した半仮面。視覚を蔽うった状態で踊ったのは、自分の見知った感覚や意識の操作を狂わせて、内的にめくるめくものを欲しいからであった。その異次元は、闇と倍音にみちていて怖ろしい。体のバランスを失いそうな危うさにおののく。しかし、ぞっとするスリルにも浸され、さっきまでの自分とははっきりと離れている処に舞い上がれる。
目を蔽って闇に立つわたしの周辺は俄かに光にみちた空間が現れだす。観客からのエネルギーを一身に浴び、受けとめきれない豊かさのなかで、見えない何かにむかって身も心も一直線に進んでいく。
作品「翔」(しょう)は稚児のイメージを妖女(シー)の姿に変えて演じた序の舞ののち、突如、能管の甲高い音の節目にのるや否や、わたしは、荒々しい鷹になり変わった。
日々にかける
作品発想の第一印象は決して失わないように、日々、インプロバイゼーションの動きをくり返し、くり返す。ダンスも文章も同じだが、次々と新しいアイディアに恵まれ、客観性と序破急を加えながら、なおも時を重ね舞台上に自分を晒す。さらに時を経ながら、いくつもの舞台で、納得のいくまで試すという経験をさせてもらった。
長年、サラバンドにのめり込んでいた私は、群舞作品、白いシリーズとして “予感=プリモニション” “コラール”を上演したが、どうしても限界を感じ、以後、振付けと演出法を180度転換させた。出演者であるダンサー達から真の動きを導き出せるのは、即興に頼る以外はなく、それが作品 “VOICE VII”になった。曲は13世紀スペインの宗教音楽の再演で混声(人々の声)に合わせた。
それは人の踊る意味を広範囲にとらえた舞台作品として多くの観客と融合でき、国の内外で幾度も上演された。これが、私の作品 “舞踊論“シリーズの最後のものになったようだ。
私の作品は「讃歌」か「挽歌」に限られたのは自然なことである。思えば多くの古人からの遺産の大きさに心から感謝する。
自由に振る舞えるようになったのは50歳以降であり、ゆれ動く楽しさ。毎日の変化の魅力。心身ともに私のピークは55歳前後の数年であった。そしてすぐに老いを迎えた。
そして遂に1996年、作品"パッセージ=径(みち)"と題して「白道」(佛教・冥府への白い道)を歩む白装束の二十人の女性群舞(曲は現代作曲家・鳥養 潮の声明による)で、私は幕を閉じた。
十年を経て、2002年の夏、「イカルスのように」が形になった。