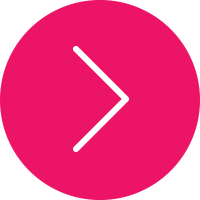Column - コラム
三条万里子論 現代舞踊作家論
by 佐藤 滋
ダンス・ワーク Vol.12 (Summer 1973)より
三条万里子の「舞踊論」は、彼女の過去の舞踊への訣別であるよりは、日本の舞踊界のバカさかげんへの彼女の精一杯の捨て台詞であった。それから約四年半ぶり、昨年十月上旬から中旬にかけて五回にわたりドイツ文化研究所ホールでひらいた「MARIKO SANJO」では、舞台を捨ててしまった彼女を目前にすることとなった。朝十時半から正午少しまで、陽の差し込むフロアーで三条を始めとする十人前後のダンサーがバッハのテープを使ってレッスンする。もちろん稽古着で、三条は途中で出てきた愛息をあやして連れ戻るという、ごく日常的な練習風景だった。そのレッスン内容は公開用に手直しした部分があるが、三条自身から聞いた所によると、マーサ・グラハム・メソッド、レスター・ホートン・メソッド、ヨガ、自然運動、その他を基に彼女自身の基本的なメソッドとして作ったもので、メソッドそのものとしても普遍性があると思い公開したとのことだ。
ここでの彼女は、産後の肉体をひとつひとつ回復させ、自らうなずきつつ動きを取り戻して行く過程を、”自然”な形で呈出していた。ここには自己の主張を押し通そうという”作家”の意識は希薄で、一人の人間としての”存在”そのものの、やすらぎを伴った確認のみがあった。おそらく彼女は、その性質としては、おだやかなタイプに属しているとは言えないだろう。むしろ負けずぎらいの意地の強いタイプではないかと思う。その彼女が、こうした形でしかその”作品”を呈示しなくなったということは並み大抵のことではない。彼女にとっても、また第三者から見ても、彼女の代表的な作品は、今もって「土偶」であり「エレクトラ」であることを考えると、現在の彼女の有り様がどれほどのものかが解ってくるだろう。
彼女の日常生活そのものの中に”もうひとつの舞踊”があったからだ。数年前に結婚した彼女は、妊娠、出産というごく日常的な事件が二度にわたり起こったのだが、彼女が自己の肉体を唯一の武器とする舞踊家だったという一点のために、出産のドラマと共に”舞踊”が姿を現したのだ。彼女は日一日と変化して行く自らの肉体を、母としての感情を込めた視線と共に、作家としての鋭くまたいつくしみを持った観察眼で凝視する。肉体の部分部分から始まったそれは、”肉体とは何か” ”人間存在とは何か”にまで展開して行く。ついには自己の肉体が最もけだかい美しさを獲得したと感じ、全ての人を前に全裸になってもいいとの衝動を持つまでに至るのだ。
このエピソードは、彼女にとっては、舞踊が舞台の枠をはるかに超えて、さらに幅広い本質的な広がりを獲得したものであったろう。だが、逆の視点を置けば、このエピソードは、何のことはない、舞踊家だったら誰もが体験することなのだ、というカラクリを持っているのではないか。そう、日常性は、その当事者においては全てが感動なのだ。さらに今回の会も、舞踊家の日常行為でしかないともいえよう。こうしてみれば、三条万里子の”舞踊”は、全て日常の中に吸収されて行く。
至純
ステップからステップの間に
by Donald Richie
The Japan Times
(1983.11.6)
日本が誇るすばらしい舞踊家三条万里子は、これまでニューヨークで活動をし、モダンダンス界を代表する芸術家の1人として広く知られてきた。その彼女がこの度帰国し、10月31日草月ホールに於いて、ピアノ曲によるブラームスを踊った。
舞踊家としての三条の評価は、これまで華麗なテクニック、劇場的センスの良さ、そして、その知性に対して与えられてきた。今回の公演では、年令に伴った熟練と経験がこれらの特性をよくとぎすませ、真に純粋なものにまで高めたものであった。
“一人のためのデュエット”と題された公演プログラムには、あの有名な、おそらく彼女の踊りの中で最もブリリアント(brilliant)で感動的な作品 “鳥” が含まれていた。が、それは、ブラームスのワルツをしめくくる形で披露された。
三条は振付の中で、よく“くり返し”を用いる舞踊家である。くり返しの中で毎回動きは微妙に変えられていく。その動きの層は、まるで各々のムーヴメントそれ自体が自律した意味を帯びはじめたかのようだった。くり返す度に輝きを増していく文学的情緒、踊りの表現領域を越えたところで、いわゆる文学や物語ではない、どこか文学作品に通じる情緒を備え持っている。
ワルツの始めに、エントリーで舞踊家として、くり返し、深く頭を下げ、お辞儀をする場面がある。それはくり返す度に、回を増すごとに厳粛に重々しく厳しいものになって行く。あるいは踊りの最後で、さながらワルツを踊っているような、やわらかい手の動きが次第に、はっきりとした拒絶を示すジェスチュアへと変わる。ライトから身を退ける彼女、白いひとつの影、激しさを増すジェスチュア。またターンのくり返し、動きのリピートの中で表現される人間の生。はつらつとした若さから苛酷な老いへと、色あせてゆくその様。踊りとして、また舞台構成として、今回の作品は感動的で彼女の精巧な意匠がうかがえるものであった。ダンサーとして、またコレオグラファーとして三条は、踊る事の重要性はポーズや型ではなく、その間にたちあらわれて描かれる孤にある事を知っている。この点において彼女は、日本の舞踊家の中でも、唯一の存在であるといえよう。
日本の舞踊においては当然の事ながら、その大部分がポーズやステップに重点が置かれている。それに対して西欧のバレエやモダンダンスではポーズとポーズの合い間、ステップからステップの間に表現されるもの-----まさにムーヴメントの流れ、それ自体が最も重要なのである。
三条は、この点を知りつくし、また知り抜いていることを一貫して踊りの中でみせる。この自覚こそが彼女の熱意と見事なテクニックと一体になり、彼女を卓越した芸術家たらしめているのである。日本の舞踊界は、以上の事を、自らの目をもって認めたはずである。
ドナルド・リッチー(訳 西澤みどり)
三条万里子の舞踊・探求抄
by 堀切敍子
舞踊研究 Vol.2 No. 4 (1986.9.30)
-
三条万里子ダンスコンサート 1982.10.29/ 12.1~4 アキライケダギャラリー
-
一人のためのデュエット 三条万里子ブラームスを踊る 1983.10.31 草月ホール
-
一人のためのデュエット 三条万里子ブラームスを踊る 1983.12.22 草月ホール
-
三条万里子ダンスコンサート 1984.9.17 新宿文化センター大ホール
-
三条万里子ダンスコンサート 1985.9.6 草月ホール
そろそろ15年程になるだろうか、三条万里子さんが2人の愛児の誕生と共に、自身も再びうまれ変わったように変貌したのは…しかし、その素地は私たちの目には見えないところで、それ以前から彼女の中に静かに在ったものなのだろう。そして、それが具体性をもって、「身体の知覚認識」としてのボディトレーニングとなって表されたといえる。それは、表層の筋肉をのみ見るのではなく、深部の、あるいは意識下域を知覚するごとくに、「からだ」と「こころ」のつながりを重視するものと思われる。その考え方は多勢の人たちに受容され、10年ほどの年月をかけてゆっくりと現在ある「三条万里子の舞踊」へと進んで来たようである。
海を超えて行き来しながら、いくつかの地でそれぞれ力強くバックアップする人たちを得て、それはまず「流体のセミオティーク」として、1982年10月・12月にアキライケダギャラリー(東京・京橋)の真白い空間に拡大された。彼女の初めてのドローイングだという、大地にずしりと根をはるような女の素描の白地のポスターが、天井、壁、床一面に貼りめぐらされ、その白一面の中で、その素描の彼女自身が動きを動き出す。地下の小さな空間の中で、観客との対話もあるそれはまさに久しぶりの“三条万里子・健在”である。そして、「しばらく、みなさん!」とにこやかに手を振りながら、「一人のためのデュエット・三条万里子ブラームスを踊る」を開いたのが1983年10月31日の草月ホールである。50才になって、再び改めて踊る力が湧いて来たという彼女は、追加公演として同年12年22日に同じく草月ホールに提示した。
その序章では、幼きものをいとおしむようにブラームスの曲はよみがえり、私たちにゆるやかなときを与えてくれ、「輪舞」は、光の道を通って、昔日の少女の初々しさを表現する。口唇から歌が流れて…..しかし、道をふりかえり呻吟する人の表情もみせ、彼女の内に何か只ならぬものが生まれているのではないかと予感させるものだ。そして、終章は、これなくしては三条万里子という人を語れないという「鳥」である。この夕、鳥は静かに光の奥深くに一人立ち、そして明るい大地に羽ばたき最後に飛び立つ姿を静かにみせて、チェロの響きと寂とした気配を脳裏に遺していた。
1984年9月17日の新宿文化センター大ホールは、客席に渦巻いていた熱気がベルの音と共におさまると、「予感」が美しい弧を描いて始まった。白いロングドレスのキリリと引き締まった背をみせたその構図には、彼女の身体への理論がすべて託され、下手から上手へと流れる円弧はまことに大胆である。二人が立ち、三人が立ち…そして流れ、止まり….常に空間は静動絢い交ぜて美しい。踊る一人ひとりは、彫像のように整えられ、彼女の理論を構築しており、さらにそれを支えているのが照明(いながきかつひこ)の演出の力である。終り近く、白い花を腕一杯に抱えた女の表情は、未来への、新しい世紀への不安の予兆であろう。「ワルツ」には、子供たちがいる。童心がある。遊び惚けて、なかなか家に帰らない大勢の子供たち。遊びの原っぱに夕暮れが訪れると母親の声が聞こえてくる。ブーツをはいた15人は時に仲良し、時にいたずらもの、時に仲間はずれ…子供の情景そのものである。そして、一夕の舞台の演出として、徐々に狭められて来た空間は、「鳥」へとさらに凝縮し、私たちは何回目かの、しかし、また新鮮な鳥を得たのである。それは、すべての人間の心の中にある鳥というものへの願望を見事に表していた。
そして、ほぼ一年ぶり、三条万里子の情熱が帰って来た。1985年9月6日の草月ホールは、まさに荘厳な聖堂と化し、白いロングドレスの「コラール」が舞った。11人の呼吸はドレスの裾の広がりにまで連なり、その空間は何故か往年の「シャコンヌ」を想わせた。そして、「ワルツ」は琥珀色の光の中でポニーテールの少女・万里子その人がブラームスと舞う。
さて、10年目の「鳥」は、秘やかな畏れと期待もって私たちの前に現れた。それは、何と強い鳥であったことか。急激に白く爆発した光は、鳥の羽を、いや人間の飛び立つ力を削ぎ落としたようだった。それは、「予感」(1984)からイメージされる彼女の未来への想いと重なり、あたかも閃光に破壊された都市までをも想像させた。しかし、それは不死鳥である。大地に打ちつける鳥の羽ばたきは白骨になろうとも身を守る武器であり、立ち上がり、飛び立つ力である。10年目の「鳥」の変容は、彼女自身の方向だろうか。その姿勢には敬嘆する。
コンサートの最後に置かれた「VOICE VII」は、85年3月9日NYのタワーで初演され、好評を博したという。誰も行く道を知らないという人生の哀しさの中に、人と連なることの楽しさを表現したこの舞踊は、客席を微笑で結んでくれた。ゆるやかなギター古代楽器の旋律と共に、黒衣姿の人たちが手をつなぎ、子供の大人も、男も女も、人形も犬も(ナント本当の犬だ!)歩き、立ち止まり、顔を会わせ円形をつくる。仮面の表情はそのたびに様々に変化して、ユーモラスな人々の時には忍者をも想わせる行列である。時が流れてゆくうちに、その黒衣を脱いで女が現れ、男が現れ、瞬時のデュエットは人間にとっての性の象徴だろうか。世代を越えて連なってゆく生命の源。人間のみでなく、生命あるもの総てへの愛情。そして、人だけでなく、人形も犬も黒衣をぬぎ、仮面の人々は尚一層生きることへの華やぎを増したように見え、客席の心には何とも言えぬ喜びが溢れてくる。この舞踊に到達した三条万里子という人の心は何だろうか。それは、生あるものへの信頼と言えるだろう。およそ50年におよぶ様々な出会いとのつながりがこの舞踊を開花させた。そして、その底にはもう一つ、共鳴し集う人々がいることは言うまでもない。
三条万里子と友人たち
サマー・ダンス・コンサート1986
by 堀切敍子
舞踊研究 Vol.2 No. 4 (1986.9.30)
-
サマー・ダンス・コンサート 1986.8.5 新宿文化センター小ホール
からだを育てる独特の考え方を基に、レッスンを開始して10数年。その結果としての「マリコ・サンジョウとフレンズ」である。そのグループにはもう既に舞踊家としての仕事を果たしている人、これから羽化するさなぎ、あるいはたまごなどなど様々だが、彼らを「フレンズ」と表現したところに三条自身の心が伺われる。2種のプログラムが組まれ、選抜されたであろう小品集とそれぞれの作家たちは、曲線でふちどられたフロアで流れるように空間をつくる。各自の表現は、次々に雑誌のページをめくるような楽しさがあり、個性豊かな色彩である。三条万里子という人間の何をどのように吸収し、体現してゆくのか。運動の技術の考え方だけでなく、何をどのように獲得するのか。それらは総て、一人ひとりにかかり、「フレンズ」と置かれたからには、単なる師弟という関係を超えた、舞踊家としての自立を育てたいという願いが読みとれる。
後半にプログラムされた三条作の「埴輪」は、軽妙な味をもつもので、黒衣たちの仕草、スケートボードの取り合わせなど、埴輪の静に対して意表をつく面白さがあり、客席は明るくリラックスした。そして、「ヴォイス」シリーズの7作目。この自在なテーマは、今回、観客参加というところに発展し、手作りの「百個をこえた」仮面と衣装が、思いもかけず楽器ケースから取り出されると、誘われた観客たちは尻込みしながらも、仮面をつけ衣裳を肩に、吟遊詩人のようなその一行の旅に加わるのだった。額縁の舞台にはみられぬ親近感をもたらしたこの試みには、この「ヴォイス」シリーズのさらなる発展と舞踊の心そのものが問いかけられている。
力尽きた鳥(繋がれた鳥)
by Marcia B. Siegel
The Village VOICE (1992.12.22)
マリコ・三条は空ではなく地上でもがき苦しみから解放されていく奇妙な鳥のような生物を踊る。三条は1960年代以来、ニューヨークそして母国である日本で舞踊公演をし続けている。彼女はわずかばかりの木々以外は何もない舞台で重要な動きから息を呑むような緊迫感をつくりだす。このソーホーからのエネルギー、精力的で密度の高い動きに満ちた1992年のダンス・シーンは衝撃である。
“Kakeri - 翔”は能舞台からの脚色だが、6名の黒装束で黒頭巾の人物が列を作って進み出るところから始まる。徐々に彼らはアキラ・ニイツ作のねじれた金網でできた木々とその近くに配置された黒い布の塚以外はなにもない空間に進み出る。すべてが不明瞭であり、あらゆる可能性をおびている。黒装束、黒頭巾の2名は重く赤い網のたれかかった、内側からぼんやりと灯りのともる籠か鉢を抱えている。彼らはその籠を高く持ち上げ幾度か空間を清めるように回る。
一人が塚の傍らにひざまずくそこから蜘蛛の巣状に影ができ、その動きは背後の壁を横切って流れを創りだす。
白装束に白い布紐で両目を覆った小さなほっそりとした人物が空間に滑り込む。
Kakeriは「鷹の井戸」を基にしたものである。これはウィリアム・バトラー・イェーツの有名な1916年の能スタイルでの舞踊の後に制作された能舞台のひとつであると思われる。「鷹の井戸」は古代アイルランド人の主人公が運命に対抗して苦労の道を選ぶというものである。おそらく三条はこの未知なるものへの畏怖と抱擁の架空のせめぎ合いの抜粋版を舞踊化したのである。彼女のソロ舞踊 “鳥” の作り直しは年齢と共に磨かれ、空へと向かう絶望感がさらに強調された終末に思える。
三条は日本の伝統である見事なまでに美しく精密な心象を結果的に生じる瞑想の核心を懸命に探し求めているのである。
マーシャ・B・シーゲル (訳 谷村元子)